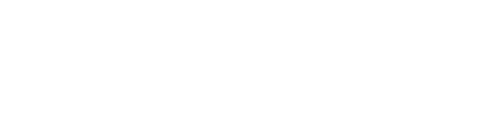実績
迎賓館庭園
庭園は、玄関前の真の庭・館内中央の行の庭・賓客宿泊室に面する草の庭の3つの庭がある。深山幽谷から流れ出る水が注ぎこむ広大な池が、まわりの建物に融け合うように配置されています。これが、古くから日本人の住まいに貫かれた伝統「庭屋一如(ていおくいちにょ)」を表現しています。 尼崎博正の監修、佐野籐右衛門を棟梁とする京都の庭師により作庭される池には錦鯉が放たれており、賓客は鯉のエサやりや舟遊びを楽しまれます。
池水量1000t、新水(補給水)、地下水濾過設備、循環濾過により常にきれいに保たれている。平成29年からは通年一般公開され、連日参観者で賑わっている。冬期は水温が5℃迄下がるが、常に元気に泳ぐ姿が見られるよう少量の餌を与えたりして万全の管理をされている。

姫路城西御屋敷跡庭園 好古園
西御屋敷跡に位置する本園最大の池泉回遊式庭園。姫山原生林を借景とする。250匹の錦鯉が生息する大池は瀬戸内海の風景を表すとされる池泉回遊式庭園群である。9つの日本庭園で構成され、其々が屋敷割遺構どおりに築地塀等で仕切られていることを特徴とする御屋敷の庭池、池水量1000t新水(補給水)地下水 池の水は循環濾過により常にきれいに保たれている。
連日多くの入園者で賑わい、近年は外国からの入園者の姿が目立ち、より賑わっています。
流れの庭池(四池)池水量250t新水(補給水)地下水築山池泉の庭池から松の庭池から夏木の庭池→流れの庭池へと四つの庭池が鑑賞できます各池には、錦鯉・草魚・メダカ・フナなど多種の淡水魚を鑑賞できます。

順正
順正書院玄関脇から石門(国の登録有形文化財)をくぐると、東山を借景に庭園が広がります。豊かな南禅寺山麓からの水の流れは1200 坪の敷地を巡り、春の芽吹きに始まりツツジ、菖蒲、蓮と花木をはぐくみます。水音に生々きと泳ぐ錦鯉、虫の音や紅葉、冬には雪景色と四季折々の優美な姿を供します。
池水量60t、30t、3tの三つの池で成り立ち、60t、30t池は地底が粘土であるため地底に拳大の石を敷き詰め、泥の濁りを押さえています。補給水は疎水からの水で、管理には気が抜けません。錦鯉にストレスを与えないよう常に駆虫剤の散布、水中ポンプジェットによる酸素補給を行っている。濾過設備が無いため、補給水のみの掛け流し式である。
冬期は水温5℃以下の時もあり、細心の管理が必要である。
8月・12月の年2回、地底の泥をあげる作業を要す。2t車1台分の泥をあげます。

山水園(湯田温泉)池泉回遊庭園
国登録有形文化財(建築物)国登録記念物(名勝地関係)
山を借景として、中心に池を置き、自然の土地の起伏を生かして池の周りに回遊路が造られている回遊式庭園です。5つの入江と1つの島を持つ池は水に接する部分が長く、美しい表情を作り出しています。二つの滝から二本の温泉水の川が池に流れ込んでおり、温泉水のせいで池の鯉は冬眠することなく、一年中元気に泳ぎ、訪れる人々を楽しませています。
池のほぼ中央に架かる石橋は特徴的で、庭園のアクセントになっています。北側の入江には自然石と石橋を、南側の入江には飛び石を配して対岸に渡れるように造られています。庭園の北側(池の上部)には「臨水」の名でお食事處として使われている離れ、臨水亭があります。池の南側には、数寄屋師・笛吹嘉一郎(うすいかいちろう)の設計・施工になる萬壽亭(まんじゅてい)があります。これは、京都桂離宮の四つ腰掛(卍亭)の写しです。
池水量400t補給水(温泉水)濾過なしの補給水掛け流し。常に温泉水が入っている。寄生虫駆除剤を散布時でも補給水を止めることは出来ず、散布には駆虫剤の量、散布の仕方などに注意をする。夏期は水温温度が38℃~39℃迄上がります。夏期の管理には細心の注意が必要です。池水温度が38℃から39℃でも餌が食べられるよう管理しています。冬期温度が18度前後になるため、給餌量を調整します。
※山水園の温泉水はひっくい病に効きます。ひっくい病の鯉も半年くらいで治る鯉もいます。

松田屋ホテル(湯田温泉)国登録記念物
作庭は七代目小川治兵衛(植治)。当初の庭園は枯山水でしたが、明治の元勲、山県有朋が命名した快活楼が建設された1918年頃に現在の庭園になる。幕末から続く湯田温泉の代表的な宿で、庭園には西郷、木戸、大久保の三者会談の小屋などが残ります。敷地面積2500平方メートル。約70匹の錦鯉を所有しています。
池水量70t補給水(温泉)掛け流し、濾過設備は沸清水97-20型1台で循環濾過をしています。
酸素補給が必要なため、水中ポンプジェットを10台設置、水温が高いほど溶存酸素が少なくなり、酸欠状態になる。夏期は水温39度まで上昇するため、細心の注意が必要になり、給餌も落ちないよう管理しています。
給餌(餌やり)は、一日量を決め、来客の方々に与えてもらうようにしています。

勝尾寺 西国二十三番札所
「勝運の寺」や「ダルマの寺」として知られる古刹。紅葉の名所で、秋が深まると約8万坪の境内の燃えるようなモミジの赤や黄色と、山の緑が織り成す見事なコントラストに圧倒される。紅葉シーズンにはライトアップも実施され、山門や本堂、参道に加え、弁天池での噴水やミスト、LEDによる幻想的な世界を演出している。池水量・弁財天池6000t、観音池100t、応頂閣池30tの三つの池があり、各池の条件に合う管理が必要とされる。
- 弁財天池6000t
夏期は水温27℃迄上昇、夏期は2度から3℃迄下がり、氷が張ることも有る為、冬から春の管理に細心の注意が必要になる。11月から4月までは餌は与えず、5月から餌付けに入る。特に餌付けの時期は給餌量の管理、天候・錦鯉の状態・水温などを観ながら決定する。 - 観音池100t
弁財天池と条件は似ているが冬に氷が張ることはなく、飼育条件は良い。 - 応頂閣池30t
補給水量が多く、夏期に21度位までしか上昇しない為、給餌量を抑える。冬期は水温12度位なので、給餌も毎日少量の冬期飼料を与えます。

城南宮 池泉回遊式庭園
昭和の小堀遠州と讃えられ、配石の素早い天才造園家、中根金作(1917~1995)は、金閣寺・天龍寺など京都の古庭園の調査・保護・修理に始まり、国内外に300もの庭園を作った偉大な芸術家です。
城南宮「楽水苑」の「室町の庭」(茶道、生花、能楽などの日本文化が大成された室町時代の様式でつくられた池泉回遊式庭園の「室町の庭」。池の中央には不老長寿を象徴する松が生える蓬莱島があり、その対岸の3っの石(三尊石)は三体の仏を表し理想の世界を象徴しています。池には錦鯉が泳ぎ、4月末の藤、5月のつつじ、秋の紅葉が特に美しい。)と「桃山の庭」が、氏が造園家として最初に手掛けた庭園で、その後「平安の庭」(平安時代の貴族の邸宅、寝殿造りの庭をモデルにした「平安の庭」。庭を広く見渡すと、寝殿造りを模した神楽殿から木々の影を写す池に続きます。この池には中ノ島があり、段落ちの滝(階段状の滝)から清流が注ぎ、2筋の遣水(やりみず・小川)が流れています。)、「春の山」更に晩年の「城南離宮の庭」と、生涯をかけて城南宮の神苑の作庭に携わりました。
池水量130t補給水(地下水)
池底は粘土である為泥の蓄積があり、飼育条件は厳しいが寄生虫駆除剤散布などで注意しながら管理している。

幾松旅館 登録有形文化財
幕末の頃倒幕運動に大きな役割を果たした維新の三傑の一人である桂小五郎(のち木戸孝允)と三本木の芸妓幾松(のちの松子夫人)の木屋町寓居跡です。
木戸孝允が没した翌日、松子夫人は剃髪染衣し翠香院と号し、お二人の想い出に溢れた当屋敷で余生をお過ごしになりました。国土の歴史的景観に寄与しているものとして、二棟が国の登録有形文化財(建造物)に登録されています。
大・中・小と三つの池から成り、総池水量が3.5tと小さめの池である。小→中→大と上から下への循環濾過(HKストレーナ-2ヶ)で流れを作っている。補給水(地下水)は夏場、水温を上げる為、少量の補給水量としています。
池は四方から建物に囲まれ、中々水温が上がらない為、夏期での給餌量・餌の種類等に注意しながら管理しています。

京都府民ホール
中立売御門前にあった旧知事公舎跡に府民ホール及び京都府公館は、昭和63年に建てられました。知事公舎時代からの大樹(えのき)を活かし、日本庭園を築造しています。庭園は桝野俊明氏、茶室は中村昌生氏によって設計され、築山に滝組みをつくり、渓流を経て池に注がれます。茶室は築山の上に建ちエノキが昔と変わらぬ勢いで空高くそびえています
池水量35t補給水(水道水)・濾過設備、セラミック濾材による循環濾過と湧清水97-10型1台の循環濾過。
補給水が水道水の為、塩素の中和剤(カルキ抜き)を毎日投入、銅板の屋根からの雨水が入り、残留銅イオン・残留塩素の測定をしています。
定期的に沪過槽、沈殿槽の清掃をしています。紫外線ランプ(殺菌灯)によりアオコの発生を抑えている。

造園部門の実績



主な実績・お取引様(順不同)
京都府 京の宿 洛兆 様/南禅寺 順正 様/株式会社 イシダ 様/滋賀県 料亭 魚数 様/Riseville 都賀山(ライズヴィル 都賀山)様 /姫路城 好古園 様/京都御所 迎賓館 様/湯田温泉 山水園 様/湯田温泉 松田屋ホテル 様/京都 幾松 様
お気軽にお問い合わせください。077-546-3350受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ